モボがみたフィンランド〜谷 譲次『踊る地平線』ヨリ
がたん!
――という一つの運命的な衝動を私たちの神経につたえて、午後九時十五分東京駅発下関行急行は、欧亜連絡の国際列車だけに、ちょいと気取った威厳と荘重のうちにその車輪の廻転を開始した。……中略……
では、大きな声で『さようなら!』
さよなら!
そしてまた『ばんざあい!』
昭和3(1928)年の春、日本を出発しシベリア鉄道で一路ヨーロッパをめざした長谷川海太郎とその妻和子が、こんどはインド洋を経由して日本郵船の客船で帰港したのは翌4(1929)年6月のことだった。
一年あまりの長旅のなかでふたりが訪れた国々を挙げてゆくと、誕生してまもないソビエト連邦にはじまり、イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル、モンテカルロ、イタリア、ベルギー、スイス、オランダではちょうど開催中のアムステルダムオリンピックを観戦し、さらにはデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、そしてフィンランドまで。文章として残されてはいないものの、ドイツやオーストリアにも訪ねているようだ。通過しただけの国は数知れず。
この長い旅の途上で見聞したことごとはキラキラした「モダーン」な文体で記録され、のちに「谷 譲次」なるペンネームのもと一冊の本にまとめられた。『踊る地平線』がそれである。
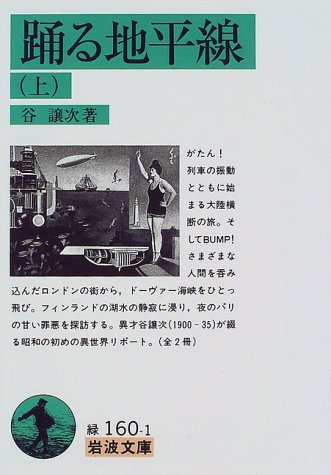
✳︎谷 譲次『踊る地平線』岩波文庫版上巻の書影。引用は、すべてこの岩波文庫版に拠っている。初版は昭和4(1929)年に中央公論社より出ている。挿画は木村荘八が担当。
踊る地平線
テムズに聴く
黄と白の群像
虹を渡る日
白夜幻想曲
ノウトルダムの妖怪
血と砂の接吻
しっぷ・あほぅい!
Mrs.7 & Mr.23
長靴の春
白い謝肉祭
海のモザイク
ほら、目次を眺めるだけでわくわくする。たとえば、シベリア鉄道の車窓を流れる寂寥とした風景はそこではこんなふうに切り取られる。
野と丘と白樺の林と斑雪の長尺フィルムだった。
家。炊事のけむり。白樺。そこここに人。
吸口のながい巻煙草――十四哥(カペイカ)。
白樺・白樺・白樺。
夕陽が汽車を追って走る。
汽車が夕陽を「追って」ではなく、シベリアの原野では夕陽が汽車を追う。荒漠としたツンドラ地帯をひた走る汽車の、その疾走感が伝わってくるようだ。「谷 譲次」の眼は、たとえて言えば色再現性に優れた高性能のカメラであり、その耳は、鋭い指向性をもった高感度の集音器である。だから読者は、いちども目にしたことのない景色にもかかわらず、あたかもじっさいに自分がいまその目で見ているかのような臨場感をもって体験することができるのだ。その文体ゆえ、ただ「モダニズム文学」のひとことで片付けてしまうとしたら、みすみすその「臨場感」をとりこぼしてしまうことになる。
手もとの岩波文庫版の解説によると、ここに収められた一連の読み物は昭和3(1928)年8月から翌年7月までの12回にわたって雑誌「中央公論」に連載されたとある。これは、とても重要だ。なぜなら、これらの文章はまさに旅の途上で書かれ、掲載され、「現在進行形で」人びとの目に触れたことを意味しているからである。つまり、〝いまのヨーロッパの空気感〟をダイレクトに読者に届けようという意図がそこにはあり、それゆえなにより重視されたのはその文章が放つ〝鮮度〟だったのだ。
たしかにいまとなっては、横文字まじりでペダンティックな彼の文章はかならずしも読みやすいとは言えないところがある。けれども昭和3年の読者、おそらくほとんどのひとが生涯に一度の「洋行」すらすることのできなかった時代にあって、それどころか異国の風土や文化、人びとにかんするまともな情報さえほぼ手にできなかった時代に、髪の毛の一本一本、シルクのドレスの襞のひとつひとつまでコトバで描き切ろうとする「谷 譲次」の文章の解像度は欠かさざるべき優れた能力だった。その意味では、「特派員」という名目で彼らをヨーロッパに送り出した当時の中央公論社の社長、嶋中雄作の眼力にもまた舌を巻く。
ここまでで、もしこの『踊る地平線』に興味を抱いたというひとがいれば早速じっさいに手に取っていただくとして、ここでは個人的に関心の高いことがら、「戦前の日本人と北欧とのつながり」に注目して「白夜幻想曲」と題された一章、とりわけフィンランドの印象をつづった「SUOMI」というエッセーについてすこし感想めいたことを残しておこうと思う。ちなみに「SUOMI(スオミ)」とは、フィンランド語で「フィンランド」の意味である。
『踊る地平線』の記述をそのまま信用すれば、「谷 譲次」こと長谷川海太郎夫妻が初めてフィンランドの地を踏んだのは昭和3(1928)年の「夏のおわり」のことだった。ふたりは、雨のストックホルムの港からバルト海のアーキペラゴ(群島)を縫うようにして一昼夜かけてヘルシンキに到着する。日本きってのモボとモガの目に、その都市はこう映った。「密林と海にかこまれた、泣き出したいほどさびしい貧しい町」。
その当時のフィンランドといえば、ロシア革命の混乱に乗じた独立宣言からようやく10年を経たばかりの「世界で一番あたらしい独立国」、「世界で一ばん古い独立国からの旅人」には「何だか『国家』の真似事をしているようで妙に可愛く微笑みたくなる」いっぽう、その「素朴さ」や「真摯な人心」「進歩的な態度」に触れフィンランドの将来に「何かしら健全で清新なもの」を感じもするのだった。
そして、おそらくこうした感想は、当地で出会ったフィンランドの人びととのふれあいの中ですこしずつ醸成されていったものだったろう。
彼らが宿泊したホテルでは、日本人の夫婦が「舞い込んで来た」というので大騒ぎ、番頭が大得意で町の案内に立ったはいいがさして珍しいものがあるわけでなく、しかもあっという間にネタが底をついてしまう。「もうありませんな」と困ってしまった番頭を、「まあ君、これだけ見せてもらえばたくさんです。そう悲観したもうな」とかえって慰める始末……。ヨーロッパのはしっこで、彼らは思いがけず素朴で善良な人びとを「発見」する。名所旧跡が少ないのは、フィンランドの、いまもむかしも変わらぬ観光地としての「弱点」かもしれない。

✳︎1929年のフィンランドの首都ヘルシンキの中心部。左手に見えるのが中央駅(1919年 設計エリエル・サーリネン)。現在とさほど変わった印象は受けない。
長いことスウェーデンとロシアという大国に挟まれ苦渋を舐めてきたフィンランドの歴史的、政治的状況も、彼はその嗅覚で敏感に感じ取っている。
国語もふたつ使われて、上流と知識階級はスウェイデン語を話し、他はフィニッシである。だから町の名なんかすべて二つの言葉で書いてある。語尾に街(ガタン -gatan)とついているのが瑞典(スウェーデン)語、おなじく何なに街(カツ -katu)とあるのが、芬蘭土(フィンランド)語で、地図も看板もそのとおりだから、旅行者はすくなからず魔誤々々してしまう。
いまでこそ国内では一部地域を除いてほとんどがフィンランド語を使用しているが、まだ1920年代にはスウェーデン語の方が優勢だったことがわかる。じっさい、文化的側面から民族主義を用意した人びと、またみずから旗振り役となって独立への気運を高めた人びと、フィンランド語の公用語としての地位向上の重要性を説いた学者のスネルマン、愛国心の高揚に尽力した作家トペリウス、独立の英雄マンネルヘイム将軍、民族叙事詩『カレワラ』を題材にした作品を数多く残した画家のガッレン=カッレラ、ご存じ作曲家のシベリウスといった人びとも、みなじつはスウェーデン語を母語とするスウェーデン系フィンランド人であった(ちなみに、「ムーミン」のトーヴェ・ヤンソンも)。
移動の車中では、おもしろい出会いもあった。「日露戦争に勝ってくれてまことに有難い」と、たまたま乗り合わせた「村の弁護士」ヴァンテカイネン氏なる人物からカタコトの英語で出し抜けの〝表敬訪問〟を受けたのだ。「ムツヒト殿下さま、クロキ・ノギ・トウゴ――当時私たちは血の多い青年でした。あの興奮はまだ強く胸に残っています」。
よく、フィンランドが独立できたのは日露戦争で日本がロシアをやっつけたおかげである、そのためフィンランドの人びとはバルチック艦隊を撃破した東郷平八郎を英雄視していて、とうとう「東郷ビール」という銘柄までつくってしまった、などと言われることがある。日露戦争によって帝政ロシアが弱体化、それがきっかけで「ロシア革命」を誘引し、その混乱に乗じてフィンランドが独立宣言をしたわけだから、たしかに間接的にはそういった側面があるし、この車内でのエピソードを読むかぎりそういう考えをもったフィンランド人も90年近く前にはまだ少なからず存在したのだろう。ただし、「東郷ビール」にかんしていえばそういう銘柄がじっさいにあるわけではなく、とあるビール会社の商品に世界の「提督」をあしらったシリーズがあり、その中に東郷元帥の肖像をあしらったデザインのものが含まれているというのが真相。「昔話」にいろいろ尾ひれがついて、気づけば「伝説」になっていたといったところか。
さて、この椿事に「谷 譲次」夫妻はいったいどう対応したのだろう。ふたりは、「ヴァンテカイネン氏」が「じつによく日本と日本の固有名詞を知っている」ことに感心しつつも、肝心の「日露戦争」うんぬんについては「(日露戦争は)私の五歳の時だから、私にとっては歴史と現実のさかい目にすぎ」ず「しごくぼうっと」してピンとこないと戸惑いをかくせない。だが、相手の手前そうも言い出せず、まるで「奉天旅順日本海とめちゃくちゃに転戦して、何人となく『ろすけ』を生捕りにしたような顔」で話を合わしてピンチ(?)をしのぐ。はるか90年も昔にヨーロッパの片田舎でこんな珍妙なやりとりが行われていたなんて、思わず頬が緩んでしまう。
ヘルシンキを離れた彼らは、フィンランドの中部サボ地方から東部カレリア地方へ、イマトラ、サヴォンリンナ、プンカハルユ、そしてヴィープリをめざす。
「ヴィープリ」という地名が入っているあたり、時代を感じる。かつて「ヴィープリ」は、フィンランド第二の都市であった。立派な駅舎はヘルシンキと同じくエリエル・サーリネンが設計し、1930年代初頭にはアルヴァー・アールトが近代的な図書館を手がけたことでも知られている。しかし第二次世界対戦後、ヴィープリはソ連に編入されたまま現在に至る。『踊る地平線』の旅から数えてわずか15年ほど後の話である。

✳︎フィンランド第二の都市ヴィープリの駅舎。設計はエリエル・サーリネン。現在はロシア連邦の一部となり名称も「Vyborg」と変わっている。谷 譲次が訪れたときは、まだフィンランドであった。
首都ヘルシンキについては「さびしく貧しい」とあまりいい印象を抱かなかった彼らだが、湖水地方の大自然には静かで確かな感動を覚えたようだ。
サイマ湖!
AH! 私は悦(よろこ)んで告白する。いまだかつてこんな線の太い、そして神そのもののように、深く黙りこくっている自然の端座に接した記憶のないことを。神代のような静寂が天地を占めるなかに、黒いとろりとした水が何哩(マイル)もつづいて、島か陸地か判然としない岸に、すくなくとも立ち並ぶ杉の巨木、もう欧羅巴の文明は遠く南に去って、どこを見ても家や船はおろか、人の棲息を語る何ものもないのだ。サイマ湖! ……中略……
そうすると「約束されたる裁き」の済んだ世に、それらすべてを過去のものとしてこれからまた新規の文明が伸びようとしているような感じがするのだ。事実私は、このときサイマ湖上の無韻の音をその生長の行進曲と聞いたのだった。
シベリウスをはじめ多くの芸術家の心をとらえインスピレーションをあたえてきた湖水地方の自然は、はるか遠い東の国からやってきたモダーンな青年作家の心をも静かな感動で包み込む。その静寂に支配された神秘的な光景を、新たな生命の萌芽を宿した原初の大地としてとらえるあたりに、このひとの作家としての感性のみずみずしさが感じられないだろうか。
そしてこの湖水地方のクルーズでは、ひとりの「老船長」の存在が彼らに強い印象を残す。その老船長は「英仏独語をよくし、デレッタントな博学者」で、「袋のようなサイマの水路を自分の掌みたいに心得ていて、そしていつも船橋に立ってアナトウル・フランスを読んでいた」という。「谷 譲次」が語る「サイマ湖」のイメージには、どこか「湖水の哲学者」とでも呼びたくなるような豊かな知性をたたえたこの人物の姿が重なっているようである。
つづいて訪れたプンカハルユでも、彼らの静かな熱狂はおさまるところを知らない。余談だが、昭和30年代にこの地を踏んだ日本画家の東山魁夷もまた、この風景に強い印象をうけて数々の名作を生んでいる。

✳︎東山魁夷『スオミ』昭和38(1963)年 「私は北方を指す磁針を、若い時から心の中に持っていた」(東山魁夷『森と湖と』新潮社)。彼もまた、フィンランドの原初の自然に心奪われたひとりだった。
私たちはいつまでもプンカハリュウを愛するだろう。二日滞在というのを五日に延ばしたのだったが、それでも、立ち去る時、彼女は耐(たま)らなく残り惜しげだった。必ずもう一度行こういつか――私と彼女のあいだの、これは固い「指切り」である。
フィンランド好きとして、思わず目頭が熱くなる一節。帰路、ふたりは乗り合わせた客らを「先生」にフィンランド語の単語を3つ学習する。
月――クウ(kuu)
アリガト――キウィイドス!(kiitos キートス)
そして、
サヨナラ――ヒュヴァステ(Hyvästi ヒュヴァスティ)
じつは、この「Hyvästi」という別れのあいさつ、フィンランド語を少々かじった人間にとってもなじみのないものである。じっさい、日本で手に入るフィンランド語のテキストにもまずたいがいは掲載されていないのではないだろうか。なぜか? 知り合いのフィンランド人に訊いてみたところ、この表現はもう二度と会うことのできないような長いお別れを暗に意味するのだそうだ。うかつに使うと、「アンタなんて絶交よ!」といったニュアンスにとられることもなくはないとか。ちなみに知人いわく「わたしは一度も言ったことないよ」。
白夜よ、「ヒュヴァステ」!
このエッセーは、こう締めくくられてつぎの目的地へとむかう。戦前のフィンランドの片田舎を走る汽車の車内、遠い異国からの旅人への別れの言葉としては、そう、たしかにこの「Hyvästi」こそがふさわしい。事実、「固い指切り」にもかかわらず、「谷 譲次」夫妻がふたたびこのフィンランドの地を訪れることはなかった。
この旅から帰国してちょうど6年後の昭和10(1935)年6月、「谷 譲次」こと長谷川海太郎はわずか35歳の若さで突然この世を去ってしまったからである。

✳︎「谷 譲次」こと作家・長谷川海太郎と妻の和子。長谷川は、他にも「林 不忘」「牧 逸馬」と3つのペンネームを使い分けたことでも知られる。画像参照元:「NAKACO'S CRAFT'S WEBLOG」様←貴重な写真の数々とともに「牧 逸馬」を紹介されています。必見。