動き出す!絵画〜ペール北山の夢
明治維新後の日本を、かりに人生にたとえるとしたら、やはり大正時代は青春時代であり、なにはなくても情熱だけはたっぷりあるアマチュアリズムの時代だったのではないか。東京ステーションギャラリーで開催中の『動き出す!絵画~ペール北山の夢』もまた、そんな時代を駆け抜けた芸術家たちの〝熱量〟に圧倒される展覧会である。

登場するのは岸田劉生、木村荘八、斎藤与里といった若い洋画家たちだが、その渦巻きの中心にいたのが「ペール北山」こと北山清太郎というひとりのディレッタントだった。北山は、西洋美術作品の図版、海外文献の翻訳、日本人画家たちの芸術論、展覧会評を紹介する雑誌「現代の洋画」(のち「現代の美術」)を主宰するかたわら、展覧会の運営や目録の編集、刊行をみずから買って出ることで若い芸術家たちの活動を後押しするとともにその感性を刺激しつづけた。彼ら若い芸術家たちは、無名の画家たちを援助したパリの画材屋の店主タンギー親爺になぞらえて北山のことを「ペール(親爺)」と呼んでいたという。有望な若者を見出し、たきつけるのもうまかったようだ。
また、とにかく新しいものに目がなく、じっさい誰よりも嗅覚にすぐれていた。大正時代、若い芸術家や文人たちのサロン的な役割をはたしたレストラン「メイゾン鴻之巣」の奥田駒蔵もそうだが、北山もまたそのような大正ディレッタントのひとりだった。そのことは、早々とアニメーションに目をつけ、後半生をアニメーション制作に身を捧げたことからもわかる(展示の最後には、彼がみずから手がけた短編アニメをじっさいに見ることができる)。

会場の前半には、西欧の画家たちの作品が並ぶ。セザンヌ、ゴッホ、ピサロ、シスレー、モネ、ミレー、ドガ、ルノワール、そしてロダンなどなど。若い日本の画家たちは、彼らの作品を北山の「現代の洋画」に掲載された図版を通じて知る。実物に接する機会がごく少なかったこの時代、なにより「現代の洋画」は西欧美術の最新動向を知るうえで貴重な情報源だった。だから、展覧会の前半はこれらの作品が大正時代の若者たちの目にどんなふうに映ったのか想像しながら観てゆくのが楽しい。ひなびた農村、郊外の雑木林、埃っぽい道、たっぷり水をたたえた川、人や馬車でにぎわう街角、そして市井の人びと。そうしたよく見知った光景が、圧倒的な新しさをもって絵画作品として成立していることに彼らは一様に衝撃を受け、震えるような感動をおぼえたのではないか。俺も書きたい! いや、俺にだって書ける! すぐにでも画材を抱えて外に飛び出したいような心持ちになったはずだ。
会場の後半は、いわば〝実践編〟。最初はおそるおそるなぞるように、そして少しずつ大胆に。ある者はいてもたってもいられず日本を飛び出し現地にあこがれの画家を訪ね、またある者はセザンヌやゴッホ、ミレーのように身近なモチーフに情熱をぶつけた。「文展」が旧弊なアカデミズムに支配された「サロン」なら、じぶんたちの才能はその枠にはおさまらない印象派のそれである。彼らは、北山を「タンギー親爺」になぞらえることで、じぶんたちの姿をゴッホやセザンヌに重ね合わせた。やがて、そうしたなかから斎藤与里を中心に高村光太郎、岸田劉生、萬鉄五郎らが結集し「フュウザン会」が生まれる。なかでも、力のある者は模倣から独創へと力強く脱却していった。岸田劉生や萬鉄五郎、中川一政や中村彝の絵からは、やはりそうした比類のないエネルギーが感じられて興味深い。
たとえば、岸田劉生が代々木の切通しを描いて話題になると、おなじようなモチーフで描くフォロワーが続いて現れる。あこがれ、模倣する存在だった自分が、いつしか気づけば模倣される存在に。大正という時代を貫く猛烈な速度はこんなことからもよくわかる。
最後に、そんな洋画との衝撃的な出会いをまともに食らった若い画家たちの作品から印象に残った絵をふたつ。
ひとつは、〝日本のモネ〟との異名をとる山脇信徳の「雨の夕」(1908(明治41)年)。ブルーモーメントのような青に霞んだ街並。無数の轍。路面電車。傘を手に足早に行き交う人びとの姿。湿り気を帯びた空気が伝わってくるようだ。

もうひとつは、川上涼花の「鉄路」(1912(明治45)年)。ゴッホのような強烈な色彩でありながら、真っ赤に照らされた崖を切り裂くように疾走する電車が新しい時代の夜明けを告げている。

電柱、轍、そして走る電車という当時としては新しい日常のモチーフが、それぞれ青と赤という対照的な色調で描かれている。そこに開ける世界もまるでちがう。かたや抒情、かたや熱気。若い画家たちの、世界を捕捉するまなざしの確かさに「ペール北山」ならずとも釘付けになる。
イヴォンヌ・キュルティ(Vn)と令嬢たちのレコード蒐集

夏の夜の読書は、ミステリにかぎる。そこに描かれる寂寥とした世界にしばし浸ることで脳内からクールダウン、涼を呼ぶのだ。
ここ最近では、雑誌「新青年」の初代編集長として江戸川乱歩を世に送りだしたことでも知られる森下雨村が、昭和7(1932)年に発表した探偵小説『白骨の処女』(河出文庫)を読んだ。帝都東京と新潟、ふたつの都市で発生したふたつの殺人事件が、精緻な推理と執拗な調査を進めてゆくなかで徐々にひとつに重なってゆく。その、絡み合った紐が少しずつほどけてゆくようなスリリングな展開に舌を巻き、同時に、30年型のシボレー、カフェー、ルジャ(赤)という名前のフォックス・テリヤ、ミッキーマウスの発声漫画(トーキーのアニメーション)、舶来物の嗅ぎ香水「ヘリオトロープ」、飛行機、凶器となったかつてハルビンで売られていた両刃の短刀などなど、全編に散りばめられた「モダン」なアイコンにうっとりして愉しんだ。そしてなんといっても、驚くべきはその文体の80年以上も前に書かれたとは到底信じがたい小気味よさ。「まったく古びていない!」というウラ表紙の惹句は真実(ほんとう)だった。奇跡の文庫化。〝熱帯夜の課題図書〟としてぜひおすすめしたい。
ところで、物語のなかに、新潟の海辺の屋敷に暮らす令嬢が夕食後、知り合いを応接間に招待して趣味のレコードコンサートを催す場面がある。その「令嬢」こと瑛子は、日ごろから「金屋」という屋号の蓄音器屋と懇意にしており、その日も「試聴」かたがた金屋が持参した新譜の中から3枚を購入したというほどのレコード好き。結果的に、瑛子はその晩何者かの手によって殺害され、その日招待された客たちが疑われることになるのだが、それはともかく、そこから判るのは、当時の令嬢の趣味のひとつに「レコード蒐集」があったということである。
ここに一枚の写真がある。蓄音機の前で、レコードを手に微笑む令嬢の姿。

この写真のオリジナルは、雑誌「ホーム・ライフ」の昭和11(1936)年1月号に掲載されたもので、写っているのは通俗小説の世界で一世を風靡した作家・加藤武雄の娘たちである。大型の蓄音機の前には火鉢が置かれ、床の間には軸が掛かっている。その取り合わせがなんとなくちぐはぐで面白い。ふたりの娘もともに和装である。
「ホーム・ライフ」は、大阪毎日新聞から発行されていたグラフ誌で、昭和10(1935)年に創刊されている。この「ホーム・ライフ」に掲載された写真を手がかりに、戦前の華族や富裕層の暮らしぶりの一端に触れようという津金澤聰廣監修『写真で読む昭和モダンの風景 1935年ー1940年』(柏書房)によれば、格調高く、戦時色を極力排したその誌面は中流以上の家庭の女性を中心に、日本に在留している外国人やロンドン日本人クラブ、海軍軍人などにも広く愛読者を持っていたという。藤田嗣治、鈴木信太郎、東郷青児ら当時の有力な画家たちが手がけた表紙からも、〝戦前モダニズムの見本帖〟といった趣がある。
先ほどの写真に戻ると、次のようなキャプションが付されている。「お小遣いで買い集めたレコードが2,000枚を超えた。父も文壇屈指のレコード愛好家」。安価でレコードやCDを買うことのできる現代におきかえても、「2,000枚」といえば相当のコレクターといえる。友人らを招いてのホームコンサートもたびたび開かれていたにちがいない。
はたして、当時の「令嬢」たちはどんな音楽に耳を傾けていたのだろう? ぼんやりそんなことをかんがえていたある日のこと、たまたま出会ったのが1920年代から30年代に数多くのレコードを吹き込んだフランスの女流ヴァイオリニスト、イヴォンヌ・キュルティの音源だった。
イヴォンヌ・キュルティ…… はじめて耳にする名前だ。甘やかなポルタメント、ときにちょっと引っかかるような歌い回し、薔薇のように匂い立つヴィヴラート…… 前時代的と言ってしまえばそれまでだが、古き良き時代のおおらかな演奏にはまた曰くい言い難い独特の魅力がある。
ただ、やはり現代の耳には10曲、20曲と立て続けに聴くのはしんどい。その「甘さ」に胃もたれを起こしてしまうのだ。けれども、ここでだいじなことは、こうした演奏は78回転のSP盤によって聴かれていたという事実である。12インチの収録時間は最大で片面5分前後、10インチだと3分程度だった。
令嬢たちのいる応接間では、慎重にSP盤に針を落とすと3分ほどのごく短い演奏にうっとり耳を澄まし、針を上げ、「リプトン」や「トワイニング」をすすりながら大人びた口調で感想など述べ合い、その後ふたたびレコードを裏返して針を落とす、そんななごやかな「儀式」が執り行われていたのではないか。そうかんがえると、そんなSP盤の時代にあってキュルティの演奏を聴くことは、小さいながらも濃厚なクリーム菓子をつまむようないかにも〝令嬢好み〟な愉悦と満足感とがあったはずだ。
Yvonne Curti plays Souvenir by Franz Drdla
いまとなっては生没年すらはっきりしないという彼女について調べるなかで出会った「日本イヴォンヌ・キュルティ協会」なるブログを拝見していたら、興味深い写真をみつけた。それは、1947年に発行されたフランスの雑誌に掲載されたもので「イヴォンヌ・キュルティ女史率いる女流楽団」という見出しのもと、10名ほどの女性弦楽器奏者たちをの姿をとらえた集合写真なのだが、右手にひとりヴァイオリンを小脇に挟んで立つキュルティと思われる人物をみることができる。黒いスーツに純白のネクタイを結び、左手をポケットに入れたその姿はなかなか凛々しい。このオーケストラがどのような活動をしていたのかその詳細については結局わからずじまいだったのだが、時期的にあるいは第二次世界大戦と関係があるかもしれない。いずれにしても、キュルティというひとがかなり旺盛な演奏活動をしていたことは推測がつく。クラシックの演奏家という以上に、その写真と表情からは、クールな表情と独特の節回しで人気を博した華のあるジャズシンガーとでもいったような雰囲気が伝わってくる。

*画像参照元: http://www.delcampe.net/page/item/id,310776808,var,LINA-DACHARY-CLAUDE-DAUPHIN-PIERRE-LOUIS-YVONNE-CURTI-ORCHESTRE-FEMININ-RADIO-47,language,E.html

- アーティスト: キュルティ(イヴォンヌ),ボーム,サン=サーンス,フォーレ,アコルディ,バーンズ,リムスキー=コルサコフ,ラフマニノフ,プニャーニ,ボッケリーニ,クライスラー
- 出版社/メーカー: オクタヴィアレコード
- 発売日: 2015/07/24
- メディア: CD
- この商品を含むブログを見る
モボがみたフィンランド〜谷 譲次『踊る地平線』ヨリ
がたん!
――という一つの運命的な衝動を私たちの神経につたえて、午後九時十五分東京駅発下関行急行は、欧亜連絡の国際列車だけに、ちょいと気取った威厳と荘重のうちにその車輪の廻転を開始した。……中略……
では、大きな声で『さようなら!』
さよなら!
そしてまた『ばんざあい!』
昭和3(1928)年の春、日本を出発しシベリア鉄道で一路ヨーロッパをめざした長谷川海太郎とその妻和子が、こんどはインド洋を経由して日本郵船の客船で帰港したのは翌4(1929)年6月のことだった。
一年あまりの長旅のなかでふたりが訪れた国々を挙げてゆくと、誕生してまもないソビエト連邦にはじまり、イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル、モンテカルロ、イタリア、ベルギー、スイス、オランダではちょうど開催中のアムステルダムオリンピックを観戦し、さらにはデンマーク、ノルウェー、スウェーデン、そしてフィンランドまで。文章として残されてはいないものの、ドイツやオーストリアにも訪ねているようだ。通過しただけの国は数知れず。
この長い旅の途上で見聞したことごとはキラキラした「モダーン」な文体で記録され、のちに「谷 譲次」なるペンネームのもと一冊の本にまとめられた。『踊る地平線』がそれである。
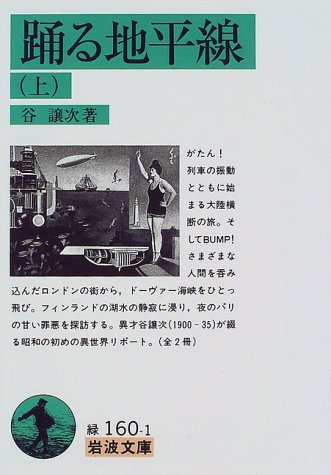
✳︎谷 譲次『踊る地平線』岩波文庫版上巻の書影。引用は、すべてこの岩波文庫版に拠っている。初版は昭和4(1929)年に中央公論社より出ている。挿画は木村荘八が担当。
踊る地平線
テムズに聴く
黄と白の群像
虹を渡る日
白夜幻想曲
ノウトルダムの妖怪
血と砂の接吻
しっぷ・あほぅい!
Mrs.7 & Mr.23
長靴の春
白い謝肉祭
海のモザイク
ほら、目次を眺めるだけでわくわくする。たとえば、シベリア鉄道の車窓を流れる寂寥とした風景はそこではこんなふうに切り取られる。
野と丘と白樺の林と斑雪の長尺フィルムだった。
家。炊事のけむり。白樺。そこここに人。
吸口のながい巻煙草――十四哥(カペイカ)。
白樺・白樺・白樺。
夕陽が汽車を追って走る。
汽車が夕陽を「追って」ではなく、シベリアの原野では夕陽が汽車を追う。荒漠としたツンドラ地帯をひた走る汽車の、その疾走感が伝わってくるようだ。「谷 譲次」の眼は、たとえて言えば色再現性に優れた高性能のカメラであり、その耳は、鋭い指向性をもった高感度の集音器である。だから読者は、いちども目にしたことのない景色にもかかわらず、あたかもじっさいに自分がいまその目で見ているかのような臨場感をもって体験することができるのだ。その文体ゆえ、ただ「モダニズム文学」のひとことで片付けてしまうとしたら、みすみすその「臨場感」をとりこぼしてしまうことになる。
手もとの岩波文庫版の解説によると、ここに収められた一連の読み物は昭和3(1928)年8月から翌年7月までの12回にわたって雑誌「中央公論」に連載されたとある。これは、とても重要だ。なぜなら、これらの文章はまさに旅の途上で書かれ、掲載され、「現在進行形で」人びとの目に触れたことを意味しているからである。つまり、〝いまのヨーロッパの空気感〟をダイレクトに読者に届けようという意図がそこにはあり、それゆえなにより重視されたのはその文章が放つ〝鮮度〟だったのだ。
たしかにいまとなっては、横文字まじりでペダンティックな彼の文章はかならずしも読みやすいとは言えないところがある。けれども昭和3年の読者、おそらくほとんどのひとが生涯に一度の「洋行」すらすることのできなかった時代にあって、それどころか異国の風土や文化、人びとにかんするまともな情報さえほぼ手にできなかった時代に、髪の毛の一本一本、シルクのドレスの襞のひとつひとつまでコトバで描き切ろうとする「谷 譲次」の文章の解像度は欠かさざるべき優れた能力だった。その意味では、「特派員」という名目で彼らをヨーロッパに送り出した当時の中央公論社の社長、嶋中雄作の眼力にもまた舌を巻く。
ここまでで、もしこの『踊る地平線』に興味を抱いたというひとがいれば早速じっさいに手に取っていただくとして、ここでは個人的に関心の高いことがら、「戦前の日本人と北欧とのつながり」に注目して「白夜幻想曲」と題された一章、とりわけフィンランドの印象をつづった「SUOMI」というエッセーについてすこし感想めいたことを残しておこうと思う。ちなみに「SUOMI(スオミ)」とは、フィンランド語で「フィンランド」の意味である。
『踊る地平線』の記述をそのまま信用すれば、「谷 譲次」こと長谷川海太郎夫妻が初めてフィンランドの地を踏んだのは昭和3(1928)年の「夏のおわり」のことだった。ふたりは、雨のストックホルムの港からバルト海のアーキペラゴ(群島)を縫うようにして一昼夜かけてヘルシンキに到着する。日本きってのモボとモガの目に、その都市はこう映った。「密林と海にかこまれた、泣き出したいほどさびしい貧しい町」。
その当時のフィンランドといえば、ロシア革命の混乱に乗じた独立宣言からようやく10年を経たばかりの「世界で一番あたらしい独立国」、「世界で一ばん古い独立国からの旅人」には「何だか『国家』の真似事をしているようで妙に可愛く微笑みたくなる」いっぽう、その「素朴さ」や「真摯な人心」「進歩的な態度」に触れフィンランドの将来に「何かしら健全で清新なもの」を感じもするのだった。
そして、おそらくこうした感想は、当地で出会ったフィンランドの人びととのふれあいの中ですこしずつ醸成されていったものだったろう。
彼らが宿泊したホテルでは、日本人の夫婦が「舞い込んで来た」というので大騒ぎ、番頭が大得意で町の案内に立ったはいいがさして珍しいものがあるわけでなく、しかもあっという間にネタが底をついてしまう。「もうありませんな」と困ってしまった番頭を、「まあ君、これだけ見せてもらえばたくさんです。そう悲観したもうな」とかえって慰める始末……。ヨーロッパのはしっこで、彼らは思いがけず素朴で善良な人びとを「発見」する。名所旧跡が少ないのは、フィンランドの、いまもむかしも変わらぬ観光地としての「弱点」かもしれない。

✳︎1929年のフィンランドの首都ヘルシンキの中心部。左手に見えるのが中央駅(1919年 設計エリエル・サーリネン)。現在とさほど変わった印象は受けない。
長いことスウェーデンとロシアという大国に挟まれ苦渋を舐めてきたフィンランドの歴史的、政治的状況も、彼はその嗅覚で敏感に感じ取っている。
国語もふたつ使われて、上流と知識階級はスウェイデン語を話し、他はフィニッシである。だから町の名なんかすべて二つの言葉で書いてある。語尾に街(ガタン -gatan)とついているのが瑞典(スウェーデン)語、おなじく何なに街(カツ -katu)とあるのが、芬蘭土(フィンランド)語で、地図も看板もそのとおりだから、旅行者はすくなからず魔誤々々してしまう。
いまでこそ国内では一部地域を除いてほとんどがフィンランド語を使用しているが、まだ1920年代にはスウェーデン語の方が優勢だったことがわかる。じっさい、文化的側面から民族主義を用意した人びと、またみずから旗振り役となって独立への気運を高めた人びと、フィンランド語の公用語としての地位向上の重要性を説いた学者のスネルマン、愛国心の高揚に尽力した作家トペリウス、独立の英雄マンネルヘイム将軍、民族叙事詩『カレワラ』を題材にした作品を数多く残した画家のガッレン=カッレラ、ご存じ作曲家のシベリウスといった人びとも、みなじつはスウェーデン語を母語とするスウェーデン系フィンランド人であった(ちなみに、「ムーミン」のトーヴェ・ヤンソンも)。
移動の車中では、おもしろい出会いもあった。「日露戦争に勝ってくれてまことに有難い」と、たまたま乗り合わせた「村の弁護士」ヴァンテカイネン氏なる人物からカタコトの英語で出し抜けの〝表敬訪問〟を受けたのだ。「ムツヒト殿下さま、クロキ・ノギ・トウゴ――当時私たちは血の多い青年でした。あの興奮はまだ強く胸に残っています」。
よく、フィンランドが独立できたのは日露戦争で日本がロシアをやっつけたおかげである、そのためフィンランドの人びとはバルチック艦隊を撃破した東郷平八郎を英雄視していて、とうとう「東郷ビール」という銘柄までつくってしまった、などと言われることがある。日露戦争によって帝政ロシアが弱体化、それがきっかけで「ロシア革命」を誘引し、その混乱に乗じてフィンランドが独立宣言をしたわけだから、たしかに間接的にはそういった側面があるし、この車内でのエピソードを読むかぎりそういう考えをもったフィンランド人も90年近く前にはまだ少なからず存在したのだろう。ただし、「東郷ビール」にかんしていえばそういう銘柄がじっさいにあるわけではなく、とあるビール会社の商品に世界の「提督」をあしらったシリーズがあり、その中に東郷元帥の肖像をあしらったデザインのものが含まれているというのが真相。「昔話」にいろいろ尾ひれがついて、気づけば「伝説」になっていたといったところか。
さて、この椿事に「谷 譲次」夫妻はいったいどう対応したのだろう。ふたりは、「ヴァンテカイネン氏」が「じつによく日本と日本の固有名詞を知っている」ことに感心しつつも、肝心の「日露戦争」うんぬんについては「(日露戦争は)私の五歳の時だから、私にとっては歴史と現実のさかい目にすぎ」ず「しごくぼうっと」してピンとこないと戸惑いをかくせない。だが、相手の手前そうも言い出せず、まるで「奉天旅順日本海とめちゃくちゃに転戦して、何人となく『ろすけ』を生捕りにしたような顔」で話を合わしてピンチ(?)をしのぐ。はるか90年も昔にヨーロッパの片田舎でこんな珍妙なやりとりが行われていたなんて、思わず頬が緩んでしまう。
ヘルシンキを離れた彼らは、フィンランドの中部サボ地方から東部カレリア地方へ、イマトラ、サヴォンリンナ、プンカハルユ、そしてヴィープリをめざす。
「ヴィープリ」という地名が入っているあたり、時代を感じる。かつて「ヴィープリ」は、フィンランド第二の都市であった。立派な駅舎はヘルシンキと同じくエリエル・サーリネンが設計し、1930年代初頭にはアルヴァー・アールトが近代的な図書館を手がけたことでも知られている。しかし第二次世界対戦後、ヴィープリはソ連に編入されたまま現在に至る。『踊る地平線』の旅から数えてわずか15年ほど後の話である。

✳︎フィンランド第二の都市ヴィープリの駅舎。設計はエリエル・サーリネン。現在はロシア連邦の一部となり名称も「Vyborg」と変わっている。谷 譲次が訪れたときは、まだフィンランドであった。
首都ヘルシンキについては「さびしく貧しい」とあまりいい印象を抱かなかった彼らだが、湖水地方の大自然には静かで確かな感動を覚えたようだ。
サイマ湖!
AH! 私は悦(よろこ)んで告白する。いまだかつてこんな線の太い、そして神そのもののように、深く黙りこくっている自然の端座に接した記憶のないことを。神代のような静寂が天地を占めるなかに、黒いとろりとした水が何哩(マイル)もつづいて、島か陸地か判然としない岸に、すくなくとも立ち並ぶ杉の巨木、もう欧羅巴の文明は遠く南に去って、どこを見ても家や船はおろか、人の棲息を語る何ものもないのだ。サイマ湖! ……中略……
そうすると「約束されたる裁き」の済んだ世に、それらすべてを過去のものとしてこれからまた新規の文明が伸びようとしているような感じがするのだ。事実私は、このときサイマ湖上の無韻の音をその生長の行進曲と聞いたのだった。
シベリウスをはじめ多くの芸術家の心をとらえインスピレーションをあたえてきた湖水地方の自然は、はるか遠い東の国からやってきたモダーンな青年作家の心をも静かな感動で包み込む。その静寂に支配された神秘的な光景を、新たな生命の萌芽を宿した原初の大地としてとらえるあたりに、このひとの作家としての感性のみずみずしさが感じられないだろうか。
そしてこの湖水地方のクルーズでは、ひとりの「老船長」の存在が彼らに強い印象を残す。その老船長は「英仏独語をよくし、デレッタントな博学者」で、「袋のようなサイマの水路を自分の掌みたいに心得ていて、そしていつも船橋に立ってアナトウル・フランスを読んでいた」という。「谷 譲次」が語る「サイマ湖」のイメージには、どこか「湖水の哲学者」とでも呼びたくなるような豊かな知性をたたえたこの人物の姿が重なっているようである。
つづいて訪れたプンカハルユでも、彼らの静かな熱狂はおさまるところを知らない。余談だが、昭和30年代にこの地を踏んだ日本画家の東山魁夷もまた、この風景に強い印象をうけて数々の名作を生んでいる。

✳︎東山魁夷『スオミ』昭和38(1963)年 「私は北方を指す磁針を、若い時から心の中に持っていた」(東山魁夷『森と湖と』新潮社)。彼もまた、フィンランドの原初の自然に心奪われたひとりだった。
私たちはいつまでもプンカハリュウを愛するだろう。二日滞在というのを五日に延ばしたのだったが、それでも、立ち去る時、彼女は耐(たま)らなく残り惜しげだった。必ずもう一度行こういつか――私と彼女のあいだの、これは固い「指切り」である。
フィンランド好きとして、思わず目頭が熱くなる一節。帰路、ふたりは乗り合わせた客らを「先生」にフィンランド語の単語を3つ学習する。
月――クウ(kuu)
アリガト――キウィイドス!(kiitos キートス)
そして、
サヨナラ――ヒュヴァステ(Hyvästi ヒュヴァスティ)
じつは、この「Hyvästi」という別れのあいさつ、フィンランド語を少々かじった人間にとってもなじみのないものである。じっさい、日本で手に入るフィンランド語のテキストにもまずたいがいは掲載されていないのではないだろうか。なぜか? 知り合いのフィンランド人に訊いてみたところ、この表現はもう二度と会うことのできないような長いお別れを暗に意味するのだそうだ。うかつに使うと、「アンタなんて絶交よ!」といったニュアンスにとられることもなくはないとか。ちなみに知人いわく「わたしは一度も言ったことないよ」。
白夜よ、「ヒュヴァステ」!
このエッセーは、こう締めくくられてつぎの目的地へとむかう。戦前のフィンランドの片田舎を走る汽車の車内、遠い異国からの旅人への別れの言葉としては、そう、たしかにこの「Hyvästi」こそがふさわしい。事実、「固い指切り」にもかかわらず、「谷 譲次」夫妻がふたたびこのフィンランドの地を訪れることはなかった。
この旅から帰国してちょうど6年後の昭和10(1935)年6月、「谷 譲次」こと長谷川海太郎はわずか35歳の若さで突然この世を去ってしまったからである。

✳︎「谷 譲次」こと作家・長谷川海太郎と妻の和子。長谷川は、他にも「林 不忘」「牧 逸馬」と3つのペンネームを使い分けたことでも知られる。画像参照元:「NAKACO'S CRAFT'S WEBLOG」様←貴重な写真の数々とともに「牧 逸馬」を紹介されています。必見。
海野十三『深夜の市長』に描かれた東京を読む
探偵小説ともSFともつかない、そんな奇妙な味わいをもった小説『深夜の市長』が、雑誌「新青年」の誌上に登場したのは昭和11(1936)年のこと。作家の名前は海野十三(うんのじゅうざ)。逓信局の技師という肩書きをもつ一方、これが作家としては長編第一作であった。

海野十三『深夜の市長』(昭和11 春秋社)書影
舞台は、あきらかに東京を連想させる大都会「T市」。主人公の浅間信太郎は、司法官のタマゴとして宮仕えの身でありながら、「黄谷青二」のペンネームで探偵小説を発表する作家でもある。そんな浅間信太郎にはひとつ、風変わりな「趣味」があった。ひとの寝静まった深夜のT市を、ひとり気の向くままに散歩するのである。
物語は、ある晩、いつものように「深夜の散歩」に繰り出した主人公が、偶然殺人事件の現場を目撃したところからはじまる。何者かに殴打され気を失った主人公が意識を取り戻すと、すでにそこには犯人はおろか死体すらもみあたらず、ただクローム側の懐中時計や新品のニッケル貨幣といった証拠の品々が散乱しているばかりであった。事件に巻き込まれることを恐れながらも、つい探偵小説家らしい好奇心から証拠の品々を上着のポケットに突っ込み現場から立ち去ろうとしていたところを、運悪くかけつけた警官にみつけられてしまう。あわやというところで、路地裏に追いつめられた主人公を救ったのはひとりの年老いたルンペン。彼こそは、夜のT市にうごめく人々からの尊敬を一身にあつめる「深夜の市長」そのひとであった。
はからずも身の潔白を証明しなければならなくなった浅間信太郎は、ミステリアスな「深夜の市長」の言動に振り回されながらも、「銀座裏の十銭洋酒店(スタンド)ブレーキ」に入り浸っている年増女や「丸の内13号館の中庭にそびえ立つ高塔」を住居とするマッドサイエンティストら〝夜のひとびと〟の協力を得て謎解きに乗り出すのだが、その先にあったのは市政を揺るがす一大疑獄事件であった。〝昼間の市長〟と彼を糾弾する黒幕議員との対立が激しさを増すなか、無事、主人公は謎を解明し真犯人を突き止めることができるのか? また、はたして「深夜の市長」の正体とは?
夜の都会を舞台にした冒険譚のような疾走感にくわえて、推理小説としてはいかにもこの時代の読者がよろこびそうな〝科学的〟トリックをとりいれる一方、「深夜の市長」とその一派のエキセントリックな存在感がこの作品に妖しげな幻想味とヴィヴィッドな色彩感をもたらしユニークなものにしている。そして彼ら〝夜のひとびと〟が生き生きと魅力的に描かれていることからもわかるとおり、主人公同様、作者もまた彼らの居場所としての「夜のT市」にすっかり魅了されてしまっている。では、この「夜のT市」が作者の想像から生まれたまったくの架空の都市であるのかといえば、必ずしもそうとばかりは言い切れない。むしろ作者は、1930年代になって東京がもつようになったもうひとつの「顔」に触発されて、この『深夜の市長』という小説を着想したと考えられるからである。
大正12(1923)年の関東大震災により壊滅的な打撃を受けた東京、とりわけ下町エリアは、帝都の威信をかけた大規模な復興事業によって大きく様変わりする。この復興事業はまずなによりもインフラの整備に重点が置かれ、とりわけその「目玉」となったのが「道路」「橋」そして「公園」の3つであった。焦土と化した大地に新たに道が敷かれ、橋が架けられ、さらに公園が配置されることで、見たこともないようなモダンな顔立ちをもつ都市が誕生したのが、まさに1930年代の東京であった。

昭和5(1930)年3月「帝都復興祭」の一コマ。復興事業によって整備された幅員44メートルの「昭和通り」を行く花電車。(画像引用元:東京都立図書館「都市・東京の記憶」 様)
『深夜の市長』のなかにも、こうした新しい眺望はさまざまな場面に登場する。浅草の吉野町に暮らす主人公は、亀井戸(かめいど)の魔窟のそばに隠居する「深夜の市長」と面会するためには復興橋梁を通って隅田川を渡らなければならないのだし、また主人公を翻弄する奔放なモダンガール「マスミ」と再会するのは「早や咲きのチューリップ、ヒヤシンス、シネラリヤ、オブコニカ、パンズイなどを程よき位置に移し、美しい花毛氈が組立てられ」た昼下がりの日比谷公園だったりする。主人公の家にほど近い隅田川の両岸にわたる「墨田公園」、そして「深夜の市長」が暮らす亀戸の先の「錦糸公園」、いずれも帝都復興事業により整備され完成されたばかりの「復興大公園」であった。さらには、主人公の眼を通してこんなふうに活写された「道路」もまた復興事業によって誕生した新風景のひとつである。
「僕は橋畔を離れて、こんどは広い大通りを柳島の方へブラブラと歩みはじめた。幅員(はば)が三十三メートルもあるその大通りのまん真中を、洋杖(ステッキ)をふりふり悠然と闊歩してゆくのだった。こんな気持ちのよいことはなかった。大通りは頑固に舗装され、銀色に光る四条のレールが象眼されていた。頭の上をみると手の届きそうなところに架空線がブラブラしているし、大通りの両側のポールには大宮殿の廊下のように同じ形の電灯が同じ間隔をもってずっと向こうの方まで点いて居り、それでいてあの大きな図体をもった市街電車もいなければ、バスもいない。ときどき円タクのヘッドライトがピカリと向こうの辻に閃くばかりで、こっちの方まではやってこない。この広い大道を闊歩してゆくのは、ただ自分ひとりだった」
この「幅員が三十三メートルもある」大通りとは、復興事業の一環として整備された22の路線のうちのひとつ、幹線第6号・駒形橋通(現在の通称「浅草通り」)のことであり、昭和通の四十四メートルには及ばないまでも当時としては驚嘆するにじゅうぶんな大道路であった。コンクリートで舗装され、電気の光に照らされて鈍く光る鉄製のレール…… その未来的な光景に、思わず主人公は嘆息せずにはいられない。「なんという勿体ない通り路であろうか。なんという豪快な散歩であろうか」。
また、ある夜の散歩コースを『深夜の市長』の主人公はまるで献立を考える食通のような周到さで組み立てる。「業平橋を渡ったところを起点とし、濠割(ほりわり)づたいに亀井戸(かめいど)を抜け、市電終点猿江を渡って工場街大島(おおじま)町まで伸ばしてみよう」と。紀田順一郎も指摘しているように(講談社大衆文学館文庫コレクション版所収「解題」)、「ありきたりの魔窟などよりもこのような無機的な新興地区に耽美的な戦慄を発見」する感覚こそが海野十三の、そして「新青年」を愛読するようなモダニストたちに共通の美意識なのであって、それは1930年代の東京という「箱庭」に萌芽し純粋培養された独特の〝感受性〟の上に育まれたものであった。たとえば、復興橋梁を鉄でできた巨大な恐竜の骨のようにとらえた堀野正雄の写真、たとえば、鉄道の高架橋の下を走り抜ける市電のパンタグラフから放たれた白い閃光をとらえた藤牧義夫の木版などを見れば、この時代の都市表現が無機質なものへのまなざしから成り立っていたことは一目瞭然だ。彼ら〝マシン・エイジの申し子〟たちは、虫取り網のかわりに絵筆を、カメラを、万年筆を手に、美しい蝶々のかわりに新時代の無機質な眺望を嬉々として追いかけていたのである。

堀野正雄『カメラ・眼×鉄・構成』(昭和7(1932)年 木星社書院)より「鉄橋」

藤牧義男「御徒町駅」(昭和7(1932)年 木版・紙)
ところで、1930年代という時代はまた、「夜」が〝都市の散歩者〟たちによって発見され、スポットライトを当てられていった時代でもあった。 「夜の散歩者」といってまず思い出される存在に、写真家のブラッサイ(ブラッシャイ)がいる。カメラ片手に夜のパリを徘徊し、そこを根城にする〝夜のひとびと〟をとらえた写真集『パリの夜』(1932年)はあまりにも有名だ。〝都市の散歩者〟のひとりだった海野十三もまた、好んで深夜の都会をよく歩いたという(前出「解題」参照)。昼は役所勤め、夜は探偵小説家にして都市の散歩者。海野十三に、『深夜の市長』の主人公である浅間信太郎の姿が二重写しになる。

ブラッサイ 写真集『夜のパリ』(昭和7(1932)年 Arts et Métiers Graphiques)
魑魅魍魎が跋扈する闇の世界、もはや理性のおよばない現実と夢とのあわい…… これまでにも、「夜」はその時代時代でさまざまな描かれ方をしてきたが、パリのブラッサイや東京の海野ら1930年代の〝都市の散歩者〟たちは、では、それをどのように描いたか。彼らは、「夜」を昼間の世界とは異なるもうひとつの現実として描いた。そこは、より人間臭く、本能的に生きる〝夜のひとびと〟がつくりだすエネルギッシュな世界である。それは「ラジオ体操のアナウンサーの声とともに起き、夜の気象通報とともに睡るような多くのT市民たちには全く分からない別の世界」なのである。都市は眠っているわけではなく、昼間と同じように、いやむしろそれ以上に活気を呈しているのだが、ただ〝昼のひとびと〟だけがそれを知らない。ごく限られた、夜の散歩者を除いては。
ある深夜のこと、『深夜の市長』の主人公、浅間信太郎は江東地区をさまよい歩いているうちこんな光景を目にするのだった。
「この辺一帯は物寂しい工業地帯だった。あたりには鉄が錆びたような酸っぱい空気が澱んでいた。そしてどっちを見ても、無暗に頑丈な高塀がつづき、夜空に聳え立つ工場の窓には明々と灯がうつり、それを距てた内側で夜業に熱中している職工たちの気配が感ぜられた。何の音かはしらぬが、カーンカンと金物を打つ鋭い音が冴々と聞こえるかと思うと、またザザザーッと物をぶちまけるような高圧蒸気の音がするのである」
腹を空かせた主人公は、工場の塀ぎわに「白い割烹着にレースの布を捲いた娘」が切り盛りする一軒の中華そば屋をみつけ、荒くれた職工たちにまじって熱いワンタンをすする。「若い職工の働いている工場街なればこそ、このような妙齢の娘が結構商売をしているのだ」。このとき、作者が目にしている夜の東京は、ブラッサイのパリと同質のものである。電気設備や交通網の拡充が、世界中の夜の都市にこうした「別の世界」を出現させたのが1930年代であった。

夜の銀座風景(「アサヒグラフ」昭和11(1936)年11月11日号)(画像引用元:戦前~戦後のレトロ写真 (@oldpicture1900) | Twitter 様)
とはいえ、この時代にあってはまだ昼の世界と夜の世界とは分断されており、よって〝昼のひとびと〟と〝夜のひとびと〟とが混じり合うことはなかった。あるとすれば、それはある種の「事故」とかんがえられた。物語の中に太陽の光を異常に恐れる奇妙な幼女が登場するが、それは〝夜のひとびと〟がけっして昼の世界では生きることのできない異なる人種であることを暗示している。それぞれの世界にはそれぞれのルールがあり、秩序があった。「深夜の市長」なる夜の世界を統率する存在を作者が思いついたのも、彼がそうした見えないルール、見えない秩序を〝都市の散歩者〟として肌で実感していたからにちがいない。
けれども、ひとつの都市に夜と昼、ふたつの世界がそれぞれの仕方で同居するいわば〝共和制〟が長く続くことはなかった。次第に都市の夜は昼によって浸食されていき、いまとなってはたんなる〝暗い昼間〟に変質してしまったからである。海野は、物語のエンディングにおいてこうした変質を〝夜のひとびと〟の消失というエピソードによってすでに予見している。「美しく優しく静もり深く、そして底しれぬ神秘の衣をつけている」素晴らしい夜の顔を、それでも、ぼくらは1930年代の〝都市の散歩者〟たちのまなざしをとおして夢想することができる。なんて素晴らしいのだろう。
◎なお、この『深夜の市長』については「青空文庫|図書カード:深夜の市長 でも購読することができる。
神保町の旧「相互無尽会社」ビルディング
春。アスファルトの裂け目から、一輪のタンポポが顔をのぞかせている。旧「相互無尽会社」のビルディングも、神保町の片隅にそんなけなげな姿でたたずんでいた。

関東大震災の復興期にあたる昭和5(1930)年に竣工したこの建物は、「あたらしい東京」を象徴する建築物のひとつとして都市美協会編『建築の東京』(昭和10(1935)年)のなかでも紹介されている。施工は安藤組。現「安藤ハザマ」の前身である安藤組は、これに先立つ大正14(1925)年には分離派建築会の山田守と組み彼の意欲作である東京中央電信局の施工も手がけている。
この旧「相互無尽会社」のビルがあるのは神保町2丁目の通称「さくら通り」沿い。神保町の古書店街になじみのあるひとなら、「矢口書店の角を曲がったすこし先」と言えばピンとくるのではないだろうか。4階(一部5階)建てのビルそのものはごくこじんまりとしたものだが、スクラッチタイル貼りの端正な外観や抑制のきいた装飾からはいかにも金融関係に似つかわしい「実直さ」が伝わってくる。松葉一清の『帝都復興せり!〜『建築の東京』を歩く』(平凡社、昭和63年)によれば、かつては屋根にスパニッシュ瓦がのっかっていたようだが、残念ながらいまは改変されていて見ることができない。
ところで、この〝渋い〟ビルディングが『建築の東京』に掲載されたのはどのような理由あってのことだろう?
ひとつには、このビルディングが「復興期」を象徴するひとつの要件をみたしていたことが挙げられる。それはなにかというと、「不燃化」というキーワードである。関東大震災で焦土と化した東京にあって、「あたらしい時代の建築」にはまずなにより徹底した「不燃化対策」が求められた。じっさい、『建築の東京』に取り上げられた建物を見るとその様式こそ多種多様であるが、「不燃」という点では共通している。たとえば、浅草の「仲見世」などははたして「あたらしい東京」を代表する建築物にあたるのだろうかなどとつい考えてしまいがちだが、じつのところは大正14(1925)年の鉄筋コンクリート造、まさに「伝統的商店街の不燃化」という点で「あたらしい」のである。この「不燃化」にかんして、『帝都復興せり!〜『建築の東京』を歩く』の著者である松葉一清はつぎのような興味深い指摘をしている。「不燃化は、その意味でも『火事と喧嘩は江戸の花』と粋がる江戸を引きずった東京の終焉を意味していた」(『帝都復興せり!』「都市の位相」140ページ)。都市の不燃化は、まちの景観やライフスタイルのみならず、その土地に暮らす人びとの心性を変えてしまうほどの意味を持っていたというわけである。
そして、この時期に起こったもうひとつのこととして「商店のビル化」が挙げられる。以前なら木造の商家が建っていたような敷地に、小規模なビルディングが林立するようになったのだ。大型化する百貨店に客を持ってゆかれ、規模の小さい商店もビル化によって対抗せざるをえないような状況になっていたのだろうと松葉は指摘している。いわゆる「ペンシルビル」が街のそこかしこにピョコピョコと建ち始め、古い商習慣は廃れて客は合理化されたサービスをこそ求めるようになる。「江戸を引きずった東京の終焉」がここでも見てとれる。
神保町の旧「相互無尽会社」ビルもまた、この時代に一気に増加した典型的な「ペンシルビル」のひとつである。角地に建っている上、となりがコインパーキングになってしまっているせいでその薄い直方体がいっそう強調されてみえる。まるで、お皿の上で倒さないと食べにくいチョコレートケーキみたいだ。
太陽が傾き時計の針が5時を指すと、洋装のタイピストや三つ揃いに中折れ帽の会社員たちがこのケーキのような建物の中からぞろぞろ出てきて、家路につく様子を想像するのはなんとなく楽しい。電車道に出てまっすぐ帰宅する者もいれば、あるいは夜店を冷やかしたり、はす向かいにあった「東洋キネマ」に寄り道する者もあったかもしれない。昭和6(1931)年版『ポケット大東京案内』の地図によれば、白山通りから旧「相互無尽会社」ビルまでのこのあたり、かつては夜店が並びずいぶんと賑わっていたようである。この建物がここに生き残っているかぎり、ぼくはそんな〝過去〟を想像し、感じることができる。
ひとつの建物が壊されるとき、それはただ「場所」が空白になるということだけを意味しはしない。ぼくらもまた、自分らの生きてきた「時間」から根っこを引き抜かれるのである。

竣工当時の面影が残る画像。画像引用元:「銀行の封筒収集〜ライフワーク〜」様
「子供之友」昭和5年6月号の岡本帰一
板橋区立美術館で「描かれた大正モダン・キッズ〜婦人之友社『子供之友』原画展」をみた。学生だったぼくは、松本竣介や長谷川利行といった名前をこの美術館で知り、また〝池袋モンパルナス〟界隈の有名無名の洋画家たちの作品の多くとここで出会った。まだ尾崎眞人さんが学芸員をなさっていたころの話だ。
「子供之友」は、羽仁吉一・もと子の「婦人之友社」が創刊した少年少女向けの雑誌である。ふたりは雑司ヶ谷の上り屋敷、いまの西武池袋線の池袋駅と椎名町駅とのちょうど真ん中あたりに社屋と自宅を建てて移り住み、そのタイミングで「子供之友」を創刊した。さらに、その数年後、近所に「自由学園」を創設している。池袋のこの土地を、自分たちの理念によった新時代の教育活動の拠点にしようとふたりは考えていたのだろう。「子供之友」という媒体に新しい時代の気風をみようという今回の展示もまた、広い意味で〝池袋モンパルナス〟界隈の物語をあつかっており、その点ではこの展示をこの美術館でみられたことは個人的にうれしいことだった。

まずはゆっくりと、戦前の子供になったつもりで表紙や挿絵として使われた原画が時代順に並べられた展示室を進んでゆく。
大正3(1914)年の創刊当初、表紙をはじめ数多くの挿絵を描いたのは北澤楽天という人物。早くから新聞や雑誌に風刺漫画を発表し人気を博した大家とのことだが、モダンというよりはむしろどこか懐かしいしっかりと描き込んだ「絵」という印象である。翌年になると、やはりすでに「人気者」だった竹久夢二が頻繁に絵筆をとるようになる。断続的にとはいえ、夢二が死の床につく昭和9(1934)年まで20年近くにわたって得意の「美人」ではなく、無邪気な「子供たち」の姿を描き続けたというのは知らなかった。
モダンの風が「子供之友」の表紙に吹きはじめるのは、震災後、ベルリン帰りの村山知義、自身の作品を〝童画〟と呼んだ武井武雄らが登場するようになってからだ。
楽天や夢二が、ぼくたちわたしたちの世界の延長線上にひらけた眺めを描いたとすれば、村山知義や武井武雄らが描いたのはまったく次元の異なる世界、甘やかなファンタジーの国の情景だった。彼らの原画のむこうには、ときに目をキラキラと輝かせながら、またときにうっとりとした表情で絵本に見入る子供たちの姿がみえてくるようである。
思わず、一枚の絵の前で足が止まった。昭和5(1930)年6月号の岡本帰一が手がけた表紙である(画像参照)。

若草色を背景に2羽のガチョウが車を引いている。ガチョウを操っているのは黄色い帽子、黄色い洋服姿の女の子。この表紙に感じられる「モダンさ」はしかし、かならずしもその絵のせいばかりとはいえない。むしろ、その優れたグラフィックのセンスによるところが大きいのではないだろうか。足元に絵とは直接関係のない白い花を並べてみたり、あえて色数を抑えて画面全体の統一を図ろうとしたりと、隅々にまで作家の意識が行き届いていることに感心する。細い糸で縫いこまれたような「kiichi」のサインも洒落ている。
面白いのはタイトルで、当時の雑誌にはまだロゴデザインという考え方がなかったのか、(おそらく)表紙を担当する画家がそれぞれまちまちに描いているのだが、ほとんどは絵の添え物といった感じであまり凝ったものはみあたらない。ところが、この岡本帰一が担当した号のタイトルはどうだろう! なんてすてきな、ワクワクするような仕上がりではないか! デザインの重要性に気づいた20年代の画家たちが、絵の世界に「モダンさ」という風穴をあけた。ときに、「子供之友」はそうした〝モダン派〟の作家たちの愉しい実験室だったのだろう。そのことは、10年代後半、この雑誌が「観音開き」や「片面開き」といった凝った仕掛けをさまざま採用していることからもわかる。
やがて誌面は次第に戦時色を反映するようになってゆくが、表紙ではあいかわらず世界の子供たちが描いた絵のシリーズや自由学園の生徒による創作シリーズなどさまざまな試みが続けられる。この〝愉しい実験室〟は、用紙制限のためやむなく「婦人之友」に合併するかたちで廃刊となる昭和18(1943)年まで続いた。
レーモンドの教文館・聖書館ビル
『日本近代建築の父アントニン・レーモンドを知っていますか〜銀座の街並み・祈り』という展示が、いま銀座の老舗書店・教文館でひらかれている。
近藤書店・洋書イエナ、福家書店、旭屋書店……街からどんどん〝活字〟が駆逐されてゆく銀座にあって、いまや教文館には唯一残された〝良心〟といった趣がある。銀座に行けば、だからたいがいは教文館も覗くし、もちろんそれがアントニン・レーモンドが手がけた建物であることも知っていた。にもかかわらず、現在の姿をみるかぎりこの建物にそれほど惹かれもしないのはどうしてなのか。
カーソルを「昭和8(1933)年」に合わせてみる。教文館・聖書館ビルが竣工した年だ。

画像引用元:小冊子「教文館ものがたり」
銀座通りに面した「教文館ビル」の83年前のその姿は、なんと美しく、またモダンなのだろう。エントランスには控えめながら印象的な装飾が施され、階上には、現在は失われてしまったがアールデコ調の塔がそびえ立っている。
写真でみるかぎり、それは設計までしたものの工事途中(1930年ごろ)で手を引くことになった築地の聖路加国際病院の「塔」、そして昭和13(1938)年に竣工した西荻窪の東京女子大学礼拝堂の「塔」とともに、いわば「3兄弟」ともいえる造型を備えているのがわかる。
いまも「長男」と「末っ子」が健在であることを思うと、「次男」の不在がかえすがえすも残念である。ちなみに隣り合わせに建つ「聖書館ビル」の階上にも同様の「塔」が存在していたが、こちらは航空写真でみるとどうにかニキビの跡のような凸凹を確認することができる。
展示がおこなわれている最上階のウェンライトホールから、同時開催の『教文館ものがたり〜明治・大正・昭和・平成の130年』を観るため3階へと移動した。震災や戦争、そして経営難など、幾度もの危機を乗り越えてきた教文館のあゆみを多数の写真を通じて知ることができるのだがなかなかこれが興味深かった。というのも、例の「塔」が失われてしまった経緯がわかったためである。
昭和31(1956)年、武藤富男なる人物が専務として招かれる。当時「キリスト新聞社」の副社長であった武藤は、裁判官出身で旧満州国では官僚も勤めたほどの実力者。その腕を買われ、経営危機に直面した教文館を再建させるための抜擢であった。その期待に応え、就任後6年をかけて武藤は経営を軌道に乗せることに成功するのだが、そうした再建策の一環として打ち出されたのが屋上に広告塔を設置することであった。戦後の経済成長期、しかも賑わう銀座の一等地ということをかんがえれば、当然出るべくして出た方策といえるだろう。
昭和33(1958)年ごろに撮られた写真がある。

画像引用元:同上
教会建築を思わせる塔は姿を消し、いかにも昭和の高度経済成長期らしい巨大な商業広告に取って代わられている。一方、「聖書館ビル」の塔はまだそのままの姿をとどめているのがわかる。
大本営発表とは裏腹に低迷の続く日本経済を反映し屋上から巨大な広告塔も姿を消したいま、2016年、「教文館ビル」の姿はずいぶんと寒々しく映る。せめてあのアールデコ調の塔があったならと思わずにはいられないが、時代時代の状況を赤裸々に映し出す「教文館ビル」を、その意味で「生きている」建築と呼ぶことはできるかもしれない。

